今からできる認知症予防と進行を遅らせる方法|食事や運動の習慣で未来を守る
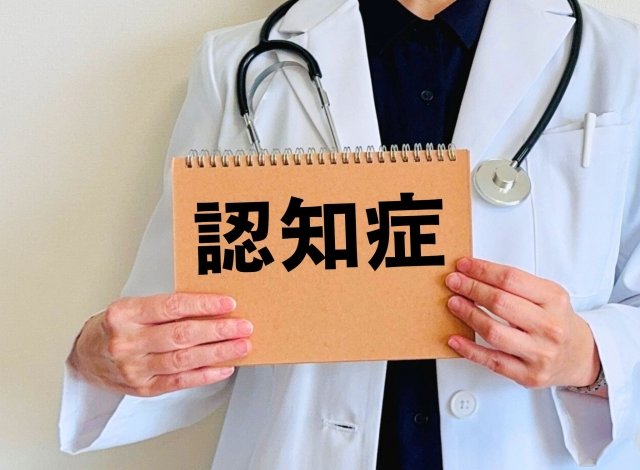
高齢化が進む日本では、認知症が要介護の原因として最も多く、誰にとっても身近な課題となっています。物忘れや判断力の低下は本人だけでなく家族の生活にも大きな影響を与え、不安や負担を増やす要因です。
認知症は完全に治すことは難しいものの、早期診断や生活習慣の工夫、薬物療法によって進行を遅らせたり発症を予防できる可能性があります。本記事では、認知症の基礎知識から予防法・進行抑制の具体策までをわかりやすく解説します。

監修
医療法人優真会 理事長
近藤匡史
順天堂大学医学部を卒業後、複数の精神科病院で急性期・慢性期・認知症医療等に従事。現在は医療法人優真会理事⾧、なごみこころのクリニック院⾧として地域精神医療の充実・発展に尽力しています。
認知症とは
認知症とは、一度獲得された知的機能が後天的に脳の障害で持続的に低下し、日常生活や社会生活に支障をきたす状態を指します。 この状態では、記憶、言語、思考、判断など複数の認知機能に障害が現れます。
認知症には主な原因疾患があり、その9割以上はアルツハイマー型認知症、血管性認知症、レビー小体関連認知症、前頭側頭葉変性症です。 中核症状(記憶障害など)のほか、幻覚・妄想や抑うつ、不安、興奮など行動心理症状も見られます。
日本では認知症が要介護の原因疾患の第一位であり、高齢化の進行に伴い患者数が増加する見込みです。
認知症は完治するのか
認知症は現時点で“完全に治る”病気とは言えません。ただし、改善可能または進行を抑えられるケースはあります。例えば正常圧水頭症、慢性硬膜下血腫、代謝異常(甲状腺機能低下症やビタミンB12欠乏など)や薬物性のものなどは適切な治療によって回復または症状改善が見られることがあります。また、軽度認知障害(MCI)の段階での早期診断と介入は進行を遅くしたり発症を予防したりする可能性が示されています。
認知症の発症を予防する3つの方法
認知症の発症を予防するには、以下の3つの方法がおすすめです。
- 脳や血管に良い栄養素を摂取する
- 有酸素運動を継続的に行う
- たくさんの趣味を持つ
それぞれ解説します。
脳や血管に良い栄養素を摂取する
認知症発症を予防するためには、脳や血管に良い栄養素を日々適切に摂ることが重要です。オメガ3脂肪酸、ビタミンB群、ビタミンEなどは神経や血管に対して良い働きをします。具体的には以下で解説します。
| 内容 | |
| オメガ3脂肪酸 |
抗炎症作用、神経保護作用などがあります。 認知機能の低下がある高齢者に対して、認知機能低下の予防になる可能性があります(1)。 |
| ビタミンB群 |
全身の代謝促進や脳の神経伝達物質の合成に関わります。 ビタミンB12や葉酸が欠乏すると認知機能障害を引き起こす可能性があります(2)。そのため、不足している場合には摂取しておきたい栄養素です。ただし、不足していない方では今のところ有効性は確認できていません。 |
| ビタミンC・E |
抗酸化作用があり、神経や血管の老化に対して効果的です。 野菜や果物から摂取可能で、一部の研究では認知機能の低下に効果があるとされていますが、明確な根拠は得られていません。 |
それぞれの栄養素は上記のような効果があり、食べ物やサプリメントから摂取するのがおすすめです。
有酸素運動を継続的に行う
有酸素運動を継続することは、認知症の発症予防に有効です。有酸素運動を最低でも半年以上続けることで、認知機能の改善や進行抑制が認められています(3)。これは、脳の容積増大を通して、注意や実行機能、記憶などの機能が改善するためです。
また、運動の内容はウォーキングよりも高強度の運動や複数の種目を週3回以上実施するとより認知症の予防につながりやすいです(4)。日常的に運動を取り入れて、認知症の発症リスクを低下させましょう。
たくさんの趣味を持つ
認知症の発症予防には頭を使う趣味を持つことが有効です。高齢者が趣味の種類を多く持つほど、認知症発症のリスクが有意に低いことが示されています。また、趣味の種類では、パソコン操作、手工芸、園芸などの趣味を実践する人は、そうでない人と比べて認知症の発症リスクが低い傾向です(5)。
これらの趣味は、計画、準備、実行のステップを伴い、また適度な身体活動を伴うことが刺激となり認知症の予防につながると考えられています。
友人などと社会的なつながりを維持する
友人などとの社会的なつながりを維持することは、心身の健康を保つうえで重要です。交流が増えると認知機能の低下やうつ傾向のリスクが軽減するとの研究結果もあります(6)。このようなつながりは孤独・社会的孤立の予防にもつながり、生活の質や健康寿命の延長に影響を与えます。 したがって、定期的に連絡をとる、集まりに参加する、小さな会話の機会を大切にすることが、認知症予防かつ健康を維持するための秘訣です。
認知症の進行を遅らせる方法
認知症の進行を遅らせるには、以下の3つの方法が効果的です。
- 薬物療法で症状の進行を抑える
- リハビリテーションで認知機能を維持する
- 生活習慣病を管理する
それぞれ解説します。
薬物療法で症状の進行を抑える
認知症の進行を抑える薬物療法は中核症状(記憶障害、失語、遂行機能障害など)に対して効果があります。主な薬剤の種類と作用は以下の通りです。
| 内容 | |
| コリンエステラーゼ阻害薬 | 脳内のアセチルコリンという神経伝達物質を分解しにくくし、記憶力や思考力を維持する働きをサポートします(7)。 |
| NMDA受容体拮抗薬 | グルタミン酸という神経伝達物質の過剰な作用を抑え、神経細胞を保護します。中等度から重度のアルツハイマー型認知症に対して認知機能や気分症状の改善が認められています(2)。 |
上記の薬剤を使用して、認知症の進行を抑制します。
リハビリテーションで認知機能を維持する
認知症の進行を遅らせるにはリハビリテーションで認知機能を維持することが有効です。認知機能訓練や認知刺激、運動療法,回想法、音楽療法などの非薬物療法が、記憶・注意・遂行機能の改善あるいは維持に効果を示しています(8)。特に、認知課題と身体活動を組み合わせたリハビリテーションは、より刺激が高まるため認知症の進行に効果的と考えられます。
生活習慣病を管理する
高血圧・糖尿病・脂質異常症・心疾患などの生活習慣病は、脳の血流や神経細胞に悪影響を与え、認知症の発症や進行に関わります。中年期の高血圧・糖尿病・脂質異常症は認知機能低下および認知症の強い危険因子です(2)。そのため、血糖値・血圧・コレステロールを適切な範囲に保つことが認知症の進行遅延に効果があります。
よくある質問
認知症の兆候にはどんなものがある?
認知症でよくある症状を以下の表にまとめました。
|
記憶障害 |
|
| 時間・場所 |
|
|
理解力 |
|
| コミュニケーション |
|
|
感情・性格 |
|
これらの症状が見られる場合、認知機能の低下が始まっているかもしれません。
認知症の予防にコーヒーは効果的?
毎日コーヒーを1杯以上飲む人は、コーヒーを1杯未満しか飲まない人に比べて、認知機能低下のリスクが 46%低下するという研究結果があります(9)。ただし、認知症を予防できるとは断定できないため、過度に期待するのは避けましょう。
認知症治療薬を飲まないとどうなる?
認知症治療薬を飲まないと、認知機能の低下が速く進行する可能性があります。例えば、アルツハイマー病の薬を中止した例では、6ヶ月の無投与期間後にプラセボ群と同じ速度で認知機能の低下が見られたという結果もあります(10)。また従来の薬、アセチルコリンエステラーゼ阻害薬(ドネペジルなど)をやめると、記憶や判断力、日常生活動作(ADL)の機能が悪化し、行動・心理症状(BPSD)が増えることがあります(11)。
生活習慣の改善から認知症予防に繋げましょう
認知症は記憶や思考、判断力などの低下によって日常生活に支障をきたす状態で、日本では要介護原因の第一位です。完治は難しいものの、正常圧水頭症や代謝異常など一部は治療で改善する場合があります。軽度認知障害の段階で早期介入することで進行抑制の可能性も示されています。
予防には魚に含まれるオメガ3脂肪酸やビタミン類の摂取、有酸素運動の継続、複数の趣味、社会的つながりの維持がおすすめです。治療では薬物療法が進行を遅らせ、リハビリや非薬物療法も有用です。さらに生活習慣病の管理が認知症予防・進行抑制に直結します。
【参考文献】

