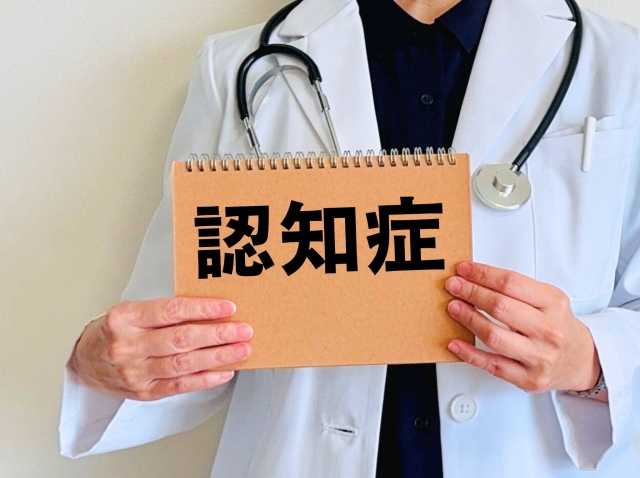4種類の認知症と軽度認知障害の症状とは?初期症状や治療方法、予防についても解説

認知症について不安を感じていませんか。「最近、家族が物忘れが増えてきた」「会話の内容を何度も繰り返す」などの兆候が気になる方もいるでしょう。認知症は単なる加齢による物忘れとは異なり、進行すると日常生活に支障をきたします。しかし、早期に発見し適切な対応を行えば、症状の進行を遅らせることが可能です。
本記事では、認知症の種類と特徴、早期発見のためのチェックリスト、進行を遅らせるための治療・予防法を解説します。認知症の進行を遅らせたい、予防したいという方はぜひご覧ください。

監修
医療法人優真会 理事長
近藤匡史
順天堂大学医学部を卒業後、複数の精神科病院で急性期・慢性期・認知症医療等に従事。現在は医療法人優真会理事⾧、なごみこころのクリニック院⾧として地域精神医療の充実・発展に尽力しています。
認知症とは
認知症とは、認知機能障害によって社会生活に支障をきたす状態です。加齢に伴う物忘れとは異なり、記憶や判断力の低下が進行し、日常生活に影響を及ぼします。一般的に、認知機能検査の結果や脳画像を基に診断が下されます。
認知症にはいくつかの種類があります。最も多いのがアルツハイマー型認知症で、脳内に異常なタンパク質が蓄積し、神経細胞が破壊されることで発症する疾患です。次に多いのが血管性認知症で、脳梗塞や脳出血が原因となり、脳の血流が悪化することで発症します。レビー小体型認知症は幻視やパーキンソン症状を伴うことが特徴です。前頭側頭葉型認知症は感情や行動の異常が現れやすく、性格の変化が顕著になります。
認知症の種類によっても症状は異なり、経過は個人差があるため、早期の診断と適切な対応が重要です。
4種類の認知症と症状
認知症は大きく4種類に分けられます。
- アルツハイマー型認知症の症状
- 血管性認知症の症状
- レビー小体型認知症の症状
- 前頭側頭葉型認知症の症状
それぞれの特徴と症状を解説します。
アルツハイマー型認知症の症状
アルツハイマー型認知症は、脳の萎縮に加えて老人斑があるのが特徴です(1)。最初に現れる症状は記憶障害で、新しい出来事を忘れてしまいます。例えば、食事をしたこと自体を思い出せなくなることがあります。
進行すると見当識障害が生じやすいです。日付や場所がわからなくなり、自宅にいるのに「ここはどこ?」と尋ねる場合があります。また、言葉が出にくくなる失語も見られ、「時計」と言いたいのに「時間のやつ」と言い換えるのが特徴的です。
さらに、身体機能への影響も現れます。ボタンの掛け違いや歯磨きの手順を忘れる、計画的な行動が困難になるなど日常動作が難しくなります。
血管性認知症の症状
血管性認知症は、脳卒中の発症後に起こりやすい認知症です。発症リスクは脳卒中後1〜10年で1.5倍、10〜30年後では1.3倍に上昇します(2)。
主な症状は、計画を立てたり順序を考えるのが難しくなる「実行機能障害」、集中力が続かなくなる「注意障害」です。例えば、料理の手順が分からなくなったり、会話の流れを追えなくなったりなどの症状です。アルツハイマー型認知症と異なり、記憶障害は必ずしも現れません。
また、脳卒中の影響で運動麻痺や嚥下障害を伴うことがあります。片方の手足が動かしづらくなったり、食事中にむせやすくなったりするのが特徴です。これらの症状がある場合、リハビリが重要になります。
レビー小体型認知症の症状
レビー小体型認知症は、中枢神経や自律神経系の神経細胞にα‐シヌクレインの凝集物が沈着して発症する認知症です(3)。主な症状は認知機能の低下に加え、幻視、パーキソニズム、妄想がみられます。
幻視は具体的で鮮明なものが多く、例えば「部屋に知らない人がいる」「小動物が見える」と訴えることがあります。パーキソニズムでは、動作の緩慢さや筋肉のこわばりが生じ、歩行時にすり足になることが特徴です。妄想は、家族や介護者への疑念として表れ、「物を盗まれた」と強く主張するケースが多くあります。
自律神経症状も多彩です。起立性低血圧による立ちくらみが頻発し、失神することもあります。夜間にはレム睡眠行動異常が見られ、夢の内容に合わせて身体を激しく動かすことがあります。
前頭側頭葉型認知症の症状
前頭側頭葉型認知症は、前頭葉と側頭葉が萎縮することで発症します。特徴的な症状として、性格や人格の変化が顕著です。
例えば、社交的だった人が急に無関心になったり、反対に無口だった人が衝動的に話し続けたりします。感情のコントロールが難しくなり、怒りっぽくなることもあります。また、適切な判断ができず、他人の気持ちを考えずに発言することが増えます。
アルツハイマー型認知症と異なり、記憶は比較的保たれるのが特徴です。そのため、日常の出来事は覚えていても、社会性や言語能力に問題が生じます。買い物中に他人の物を勝手に取る、食べ物の好みが極端に変わるなどの非社会的行動をしてしまうことも少なくないです。
軽度認知障害の症状【認知症の前段階】
軽度認知障害は、認知機能の低下がみられるものの、日常生活には大きな支障がない状態です。しかし、認知症へ移行するリスクがあるため注意が必要です。
主な症状は、物忘れの増加や判断力の低下です。例えば、昨日の食事内容を思い出せない、同じ話を繰り返すことが増えるなどがあります。また、約束を忘れたり、買い物の際に予定していた品物を思い出せなかったりすることもあります。
認知機能の低下はあるものの、会話は成立し、家事や仕事も通常通りこなせることが多いです。しかし、新しいことを覚えるのが難しくなり、複雑な作業や計画を立てるのに時間がかかることがあります。
軽度認知障害と判断された場合、認知機能を低下させないことが重要です。運動や脳トレーニングを取り入れる、食生活を改善するなどで進行を遅らせる可能性があります。
認知症の初期症状【チェックリスト】
認知症の症状が当てはまっているかチェックしてみましょう。
- 何度も同じことを言う
- 探し物が多い
- 怒りっぽくなった
- 物を盗られたと思い込んでしまう
- 時間や場所がわからなくなる
- 慣れた作業ができなくなる
- 興味や意欲が低下する
- 性格や行動が変化する
- お金の管理が難しくなる
- 身だしなみに無頓着になる
上記の各項目は自分で気づけない場合も多く、家族や友人から指摘されたことはないか思い出してみましょう。多くあてはまるほど認知症の疑いがあります。
認知症の治療方法
認知症の治療は2つあります。
- 薬物療法
- リハビリテーション
それぞれ解説します。
薬物療法
認知症の薬物療法には、主に「コリンエステラーゼ阻害薬」と「NMDA受容体拮抗薬」が主に用いられます(4)。
| 効果や副作用 | |
| コリンエステラーゼ阻害薬 |
脳内のアセチルコリン分解を防ぎ、神経伝達を促進することで認知機能改善を狙います。 副作用:吐き気や下痢、食欲不振 |
| NMDA受容体拮抗薬 |
過剰なグルタミン酸の作用を抑え、神経細胞を保護します。 副作用:めまいや頭痛、便秘 |
認知症の薬物療法は、主に症状の緩和や進行を遅らせることを目的としています。完治させるものではありませんが、生活の質を向上させるために有効な手段です。
リハビリテーション
リハビリテーションにより認知症の進行を予防し、症状の軽減を図ります。作業療法では日常生活動作を中心に、自立した生活を維持するための訓練を行います。例えば、料理や掃除などの家事動作を練習し、できることを増やすなどです。屋内環境の調整も重要で、家具の配置を工夫することで安全に移動できるようにします。
理学療法では運動を通して身体機能を維持し、向上させます。適度な運動は認知機能を高めるのに効果的です。また、精神面にも良い影響を与え、不安や抑うつを軽減します。
推奨される運動量は中等度の強度で週3回、45〜60分を12週間以上継続することです(5)。適切なリハビリテーションを取り入れることで、生活の質を向上させることができます。
認知症の予防方法
認知症のリスクを下げるためには、生活習慣の見直しが重要です。認知症の危険因子には、身体活動量の低下、社会的孤立、糖尿病、高血圧、肥満、喫煙、うつなどがあります。特に身体活動量の不足はアルツハイマー病と深く関係しています。適度な運動を続けることで、糖尿病や高血圧の予防にもつながるでしょう。
具体的には、週3回以上の有酸素運動を行うと、認知機能の低下を抑える効果が期待できます(6)。例えば、30分以上の速歩やジョギング、水泳、サイクリングなどの運動があります。軽い散歩やストレッチだけでは十分な予防効果を得るのは難しいです。中強度以上の運動を意識するとよいでしょう。
認知症の症状を理解して早期発見と予防に努めましょう
認知症は、記憶や判断力の低下により、日常生活に支障をきたす状態です。加齢による物忘れとは異なり、進行性であり、早期診断と適切な対応が重要です。認知症にはいくつかの種類があり、最も多いのはアルツハイマー型認知症で、記憶障害が主な症状です。
治療には薬物療法とリハビリテーションがあり、症状の軽減や進行を遅らせることが目的です。また、運動や食生活の改善により予防できる場合もあります。運動では、週3回以上の有酸素運動が効果的です。認知症の早期発見と予防が、生活の質を維持する鍵となります。
【参考文献】